
「アートの島」として知られる佐久島ですが、「三河湾の黒真珠」とも呼ばれていることをご存知でしょうか。
佐久島の西側には黒壁の集落があり、その景観から黒真珠と呼ばれるようになりました。この名前はギリシャのミコノス島が「エーゲ海に浮かぶ白い宝石」と呼ばれており、それに対比させて着けられたのだとか。佐久島で有名な「おひるねハウス」も黒く塗られていますね。
しかし、なぜこのような集落があるのか。この記事では佐久島の黒壁集落と、その歴史について紹介します!
目次
家を黒く塗っていた理由は「海が近くにあるため」
小さくなる黒壁集落と、それを守る運動が始まる
美しい景色から知る、佐久島の歴史
家を黒く塗っていた理由は「海が近くにあるため」

そもそも、なぜ壁を黒く塗る必要があったのでしょうか。これには、島である以上避けられない問題があるためなのです。
海の近くにある家は、潮風に乗った塩分によって金属はもちろん、屋根やドア、外壁、塗装まで全てがサビやすくなります。これを「塩害」と言びます。
サビが進行すると腐食し穴があき、雨漏りの原因になったり、サビて腐食した電気系統に雨が入り込んでショートしてしまったり、様々な害を及ぼします。
サビだけでなく、ガラスが白く曇ってしまったり、植物が枯れやすくなったり、その被害はキリがありません。しかし島であり周りが海で囲まれている以上、塩害は切っても切れない関係にあります。
そこで佐久島では、家の外壁にコールタールという黒い塗料を塗って、塩害対策をしていました。コールタールは石炭を乾留させてできるもので、船底に塗るために使われており、サビや腐食を防ぐ効果がありました。
この壁を黒く塗った家並みは島固有のものと評価され、今でも黒壁の集落が残っているという訳なのです。この景観は「島の宝100景」や「にほんの里100選」にも選ばれています。
小さくなる黒壁集落と、それを守る運動が始まる

しかし、壁に塗料を塗るのはなかなかの重労働が強いられます。また島民の高齢化が進み、もともと佐久島一帯が黒い壁だったのが黒壁の集落がだんだん小さくなっていくました。
それでもこの景観を守るべく、島民の有志が集まった「島を美しくつくる会」と行政が塗り替えを続けてきました。
2003年からは島民以外からもボランティアを募り、「黒壁運動」を開始。このような取り組みがあり、今でも黒い壁の集落が残っているのです。
佐久島のアート作品の一つ、「大葉邸」はこの黒壁集落のうちの一軒の空き家をアートとして蘇らせたもので、観光客が訪れるスポットとなっています。
美しい景色から知る、佐久島の歴史
この記事では、佐久島に黒い壁の集落がある理由と、その歴史について紹介しました。
美しい風景にも、歴史があると知るとその奥深さを改めて感じることができますね。また佐久島に訪れた際には、ぜひ歴史の観点でも黒壁集落を見てみてください。
画像参照元
http://sakushima.com/
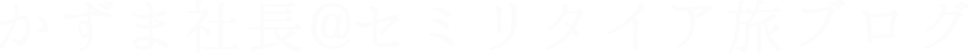


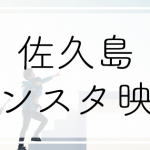






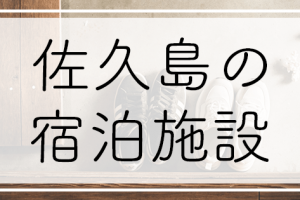







コメントを残す